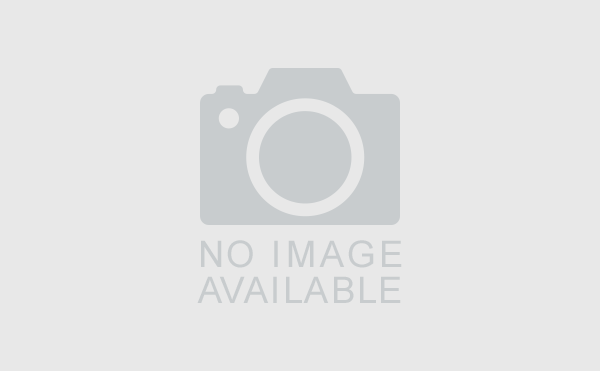中央銀行の動き
今日は、中央銀行の動きについて書いてみたいと思います。
このところ各国の中央銀行が異例の措置を行うようになってきました。
スイスの中央銀行であるスイス国立銀行は、自国通貨高阻止のために為替介入ラインを
設けてスイスフラン高を阻止していましたが、今月15日に、「今後は為替介入ラインを
撤廃して為替介入は行わない」と宣言し、スイスフラン高はやむを得ずというスタンスにいきなり変更してきました。
スイス国立銀行がこのような措置を行った要因は、今月22日のECB理事会で、いよいよ欧州ユーロ圏の追加緩和宣言が発令される可能性が高まったことが起因していると
言われています。
欧州中央銀行であるECBが追加緩和を実施すると、ユーロ安圧力が
強まることにより 対ユーロでのスイスフラン高の抑制が為替介入でも困難になってくるため、スイス国立銀行は、ECB理事会開催の1週間前というタイミングで、為替介入解除の措置に踏み切ったのではないかと言われています。
しかし、このことにより今後、スイスにはデフレ圧力が高まる恐れが出ています。
欧州ユーロ圏の追加緩和政策が、スイス国立銀行にこのような決断をさせてしまったようです。
一方、日本の中央銀行である日銀ですが、2013年の4月の異次元緩和宣言で公表した「2年後に物価上昇率2%達成」の期限をいよいよ今年の4月に迎えようとしています。
現時点での国内の消費者物価指数コアCPIの平均値は1%にも到達していない状況なので おそらく4月になった時点での物価上昇率2%達成は困難に思われます。
そのためか、日銀は昨年10月のレポートで達成目標を「2015年を中心とする期間に2%程度を達成」という表現に変更しています。
今後、日銀がこの2%程度をどのあたりまで見るのかが気になるところです。
国内の物価上昇率平均値2%達成というのは、1980年代後半のバブル期でさえ実現 できませんでした。今回の目標を2%程度とした場合でも達成は難しいと思われます。
日本は、輸出関連業よりも輸入関連業の割合が多いので円安による景気活性がしにくい
ことと、働き手がこれからも減少する傾向にあるので、物価上昇率を2%程度まで達成
するためには、追加緩和策よりも産業の構造改革を行う方が先決であると考えます。
もし、このまま、日銀が2%程度という目標に固執して追加緩和を頻繁に行っていくと、国債市場の干上がり時期が早まることになり、出口戦略が取りづらくなってしまう恐れがあります。
今後、追加緩和は、日本経済が悪化した場合のみに実施を検討すべきだと思います。
日本経済は2014年度の第1、第2四半期でGDP値は2期連続のマイナスにはなりましたが、経済が打撃を受けているわけではなく景気は堅調な状況にあります。
原油安によるインフレ抑制の懸念は確かにありますが、堅調な日本経済は、今後しばらくは原油安の恩恵により、徐々に改善の方向に向かっていくと思われます。
そして、量的緩和を終了させたアメリカについてですが、これまでは物価上昇率が2%弱で推移してきていましたが、ここにきて原油安の影響により物価上昇率が下がってきています。そのために今後は、アメリカの中央銀行とも言える連邦準備制度理事会(FRB)が、利上げを予想どおり年央あたりに実施するのかどうかが焦点になりそうです。
しかし、このような現状のアメリカ経済も堅調な状況にあります。
原油安によりガソリン代がかなり下がってきているためアメリカ国民の家計も改善されてきているようです。
日本の物価上昇率は、2年前に比べるとかなり改善しました。現状の物価上昇率で
しばらく様子を見ていくのが十分ではないでしょうか。
以上、中央銀行の動きについての記事でした。
2015年1月17日