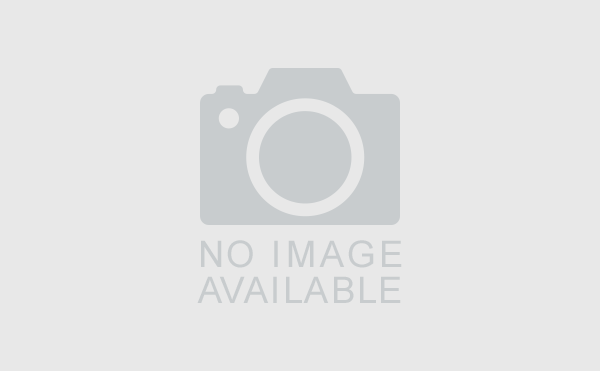マイナンバー制度とはそもそもどういうものなのか
今日は、マイナンバー制度とは何なのかについて書いてみたいと思います。
マイナンバー制度の導入が来年1月に開始されるにあたり、来月からいよいよ 住民票を持つ人それぞれに、その人特有の12桁の番号(マイナンバー)が郵送されてきます。
今後は、この12桁の番号を個人でしっかりと管理しなければならなくなります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3つの分野に関して、複数の機関が持っている情報が、同じ人が持っている情報であるということを確認するために使われるものです。
ただし、個人情報の内容自体は、各行政機関が共有できるような一元管理をされるものではなく、各行政機関内でのみ管理ができるというものです。
マイナンバー制度の導入により、年金や児童手当などの手続きで、従来、必要とされていた住民票や所得証明書などの添付が不要となることで、行政機関での処理が迅速になるとのことです。
また、2017年1月を目標に、ポータルサイトという、インターネットによる手続きだけで申請を可能にするしくみの導入が検討されており、さらなる運用の効率化も計画されています。
また、個人の任意によりますが、個人番号カードというものを発行申請して、そのカードを個人で所持することができます。
このカードにはICチップが搭載されており、個人の顔写真、氏名、性別、生年月日、住所、個人番号がデータとして登録されます。(これ以外の個人情報は登録されないとのことです。)
この個人番号カードを使うことで、コンビニでも住民票や印鑑登録証明書を発行することができるようになります。
しかし、マイナンバーは、公的機関、企業、証券会社、保険会社などの様々な所で提示しなければならない場面がでてきます。
サラリーマンの場合は、厚生年金、健康保険、雇用保険への加入や年末調整などのために企業に提示する必要がでてきます。
社会保障関連で、年金を受給する人、児童手当を受給する人、介護や福祉のサービスを受ける人などの場合は、市役所などから提示を求められることになります。
失業保険など雇用関連の給付金を受給する人の場合は、ハローワークから提示を求められることになります。
ここで、企業にマイナンバーを提示して本当に大丈夫なのかと思うのですが、万一、企業でマイナンバーが漏えいした場合、マイナンバーを扱った担当者には禁固刑などの重い処分が下され、また企業自体にも重い罰則が下されるそうです。
そのため、企業はマイナンバーの管理の厳重化を迫られることになるそうです。
また、マイナンバーは、医療情報の一部と銀行口座にも適用されるようです。
医療情報へのマイナンバー適用については、特定健康診査(メタボリックシンドローム検査)と予防接種の記録への適用となり、銀行口座へのマイナンバー適用については、利用者の任意による適用となるそうです。
適用時期については、特定健康診査の方が来年1月から、予防接種の方が2017年から、銀行口座の方が2018年からになるそうです。
しかし、来年1月から予定されていた基礎年金番号へのマイナンバー紐づけについては、年金情報漏えい事件の影響で当面見送りになるそうです。
マイナンバー制度は、行政機関の業務の効率化が最たる目的となっていますが、この制度の導入により懸念しなければならないことがあります。
その1つに、住民票を持っていない人はどうなるのかというところがあります。
これらの人への対応はどうなるのか、例えば、災害対策では、被災した人の素性をマイナンバーで特定して救済を効率よく行うとのことですが、この場合、住民票を持たない人は
どのように 扱われるのかという問題があります。
また、ポータルサイトを導入する上でのセキュリティー対策は大丈夫なのか、
また、将来、マイナンバーの制度がどのように変化していくのかも懸念すべきところかと思います。
以上、マイナンバー制度とは何なのかについての記事でした。
2015年9月25日