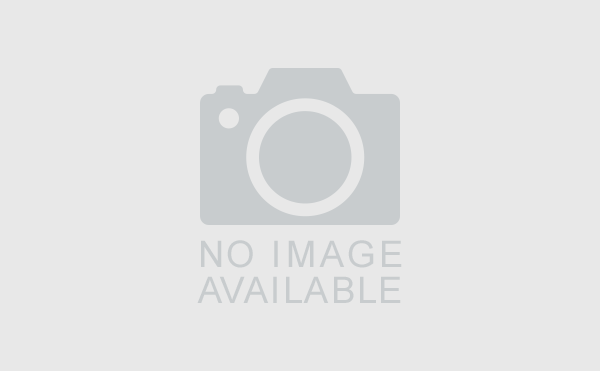物価上昇が原因なのか 日銀、長期金利の上限値0.5%を1.0%に修正
7月28日の日銀の政策決定会合において、日銀総裁より「現在の長期金利の上限値0.5%を1.0%に変更する」との発表がありました。
今後、物価上昇の上振れによる長期金利の上昇が想定されるため、前もって長期金利の上昇を1.0%まで許容する形にしておくのだそうです。
もしも長期金利が1.0%を超えそうになった場合、または投機筋による国債の売りが行われた場合には、日銀が国債の買い入れを行って長期金利の上昇を抑えるのだそうです。
一方、金融緩和については、今後も引き続き行っていくようです。
日本の長期金利がインフレ率の上昇によって上振れしやすくなっていることが、今回の発表の背景にあります。
2023年6月での日本のインフレ率(生鮮食品を除く消費者物価指数)は3.3%でした。
一方、アメリカのインフレ率は3.0%でした。
日本の方が、インフレを抑制するために更なる利上げに踏み切ろうとしているアメリカよりもインフレが進んでしまっているのです。
しかし、日本のインフレ率の大部分を占めるのは、輸入品などの物価の上昇によるコストプッシュインフレです。
経済の活性化で促されるデマンドプルインフレは進んでおらず、この指標となるサービスの消費者物価指数は、目標値2%に今だに到達していません。
ここで、長期金利上限が今の0.5%(名目金利)のままで期待インフレ率(今後予想されるインフレ率)が上昇すると、実質金利は低下しマイナスに転じますが、物価上昇の上振れによって期待インフレ率がさらに上昇して、実質金利のマイナスが大きくなってしまうと債券の売りが誘発されて、日銀の買い入れ額がさらに増えることになります。
これが債券市場の機能低下を引き起こし、金融緩和政策の維持を困難にします。
こうなった場合、日銀が抱える借金は急増することになります。
これを防ぐためにも、今の長期金利の上限値は上げなければならなかったのです。
要は、インフレの制御は容易にできるものではないため、日銀は、長期金利の変動をある程度、市場原理に委ねることにしたのです。
今回の1.0%への引き上げ措置は、日本のインフレ率が、来年からは低下していくという見立てで行われているようです。
しかし、もしも見立てとは逆にインフレ率が上がってしまったら、上限を1.0%からさらに上げなければならなくなります。
そうしないと、実質金利のマイナスがますます大きくなってしまいます。
しかし、だからと言って上限を上げてしまうと金利が上がって、日銀が抱える借金の利払いが増えてしまいます。
そのようなことから、今の物価高を早期に終息させることが不可欠なのです。
また、今回の1.0%への引き上げ措置は、国民や企業へ少なからず影響を及ぼします。
先回、長期金利幅を±0.25%から±0.5%に変更したときと同様、今回もまた、貸出金利を上げる金融機関が出てくることが想定されます。
例えば、家をローンで購入する場合の固定金利が上がるのではないかという懸念があります。
2023年7月29日