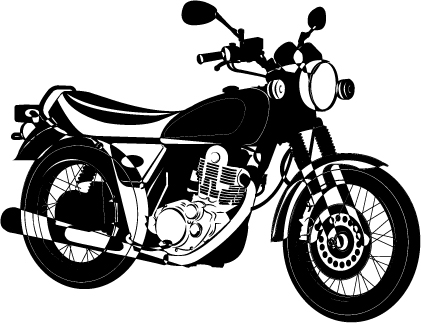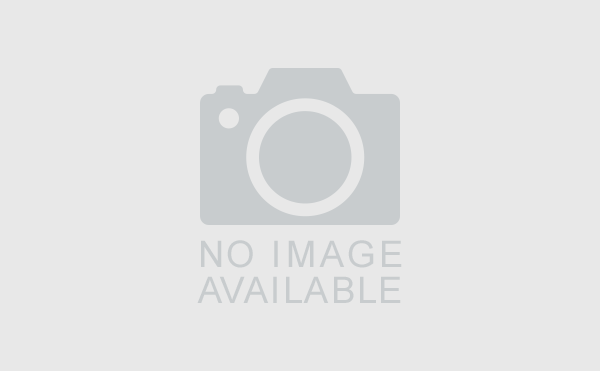バイクの電気トラブル。レギュレータ故障での一幕。
今日は、バイクの電気トラブルについて書いてみたいと思います。
先日、友人がヤマハのSRX600の中古車を買ったのですが、そのSRXが買った
その日にいきなり電気トラブルに見舞われました。
販売店から乗って家まで帰るまでの夜道で急にヘッドライトが点かなくなり、他にもウィンカーが点かないなどの状態になってしまったようです。
友人はすぐにバイク屋にこのことを連絡したところ、バイク屋は謝罪の上、「原因はレギュレータの故障だと思います。新品をすぐに送るので交換してください。」とのことでした。
そして、レギュレータが到着後、交換を行ってみたところ、ランプ類等の電気系統は正常な状態に戻りました。
(ランプの球切れは発生していませんでした。)
念のため、バッテリーの端子にテスターの端子をくっつけ、アイドリングの時とスロットルを吹かした時の電圧を測ってみたところ、
アイドリングの時は14V半ば、スロットルをどれだけ吹かしても15V前半におさまったので正常と判断しました。
(使われているバッテリーは充電電圧高めの開放型タイプ。よって、この数値で良しと判断しました。)
今回、バイク屋が間髪入れずにレギュレータが故障と考えたことで早急な対処ができたのですが、 レギュレータの役目などを以下に少し書いてみたいと思います。
バイクの電気トラブルの原因は、バッテリーの劣化によるもの、そしてレギュレータの故障によるもの、この2点がほとんどを占めています。
それぞれの発生頻度は高く、数年ごとに新品に交換する必要に迫られます。
バッテリーのトラブルは、バッテリーあがりがほとんどです。
これはバイクに乗る頻度や時間の経過とともに液の減少や内臓物の劣化が進み、
その結果、正常な充電と放電が行われなくなってしまうというものです。
セルが回りにくくなったり、ウィンカーが点滅しなくなるといった現象(経験上)に見舞われます。
一方、レギュレータの故障は、熱ストレスによるものです。バイクに乗る機会が多くなればなるほど熱ストレスがかかる度合いが高まり、そのあげくに部品の内部が破壊されてしまうというものです。
そもそもバッテリーは、エンジンを始動させるための電気の発生元としての役目と、
外部から供給される電気を充電しながらバイクの電気系統へ安定した電気を供給する役目を持っています。
その外部から供給される電気は、オルタネータとレギュレータから送られてくるものです。
オルタネータ(ジェネレータ)とは発電機のことです。
バイクはエンジンをかけるとクランクシャフトが回りますが、
クランクシャフトには磁石が入ったフライホイール(オモリ)が取りつけられていて、
これがコイルがついた鉄心(ステータ)の外周を回ることで交流の電気が発生します。
この電気が発生するユニットがオルタネータです。
また、スロットルの回し方でクランクシャフトの回転速度が変わるので、
それにともなってオルタネータの出力電圧も変動します。
したがって、オルタネータから発生される電気は不安定な交流の電気となるので、この電気を直にバッテリーに供給することはできません。
バッテリーに供給する電気は一定の直流の電気でなければならないのです。
(実際の充電電圧はバッテリーの定格12Vよりも若干高めの電圧になります。)
そこで、オルタネータから発せられる不安定な交流の電気を一定の電圧の直流の電気に
変える役目をするのがレギュレータです。
しかし、高めの電圧を一定の電圧に下げる際には、そのときの電力に応じたエネルギーが発生します。
これは中に溜めておくわけにはいかないので、必ず外に捨てる必要があります。
この捨てるべきエネルギーは熱になりますが、バイクの場合の電圧変換においてもエネルギーとして発生する熱の温度はかなり高くなります。
そのためレギュレータは、熱を発生する部品が壊れないように、部品をアルミなどのケースやフィンなどの放熱効果のある金属物にくっ付けて、熱を金属物の中へ逃がす構造になっています。
さらに金属物からの放熱を促すために、レギュレータ本体は風が当たりやすいところや金属フレームに取り付けられたりします。
ただし、SRX600のレギュレータは、シートの下の尾灯に近いところに取り付けられています。
しかし、放熱措置がされてはいても、どうしてもある程度の熱はレギュレータの中の部品に加わってしまいます。
熱が加わり続ければ、部品はもたなくなり、あるところで壊れてしまいます。
ところで、オルタネータの方は故障はしないのか?ということですが、
こちらの方は、レギュレータに比べれば故障率はかなり低いようです。
なぜなら、オルタネータは頑丈な部品を中心に構成されているからです。
コイル(銅線を巻き線にしたもの)が使われていますが、コイルは塗布されているワニスによって、絶縁耐力や蓄熱防止性能が補強されています。
ただし、バイクが苛酷な状況下にさらされていると、コイルの絶縁耐力の低下や蓄熱を招くことはありえます。
実際にコイルの焼損はまれにですが発生することがあるようです。
コイルの絶縁不良がもとで焼けたのか、銅線の接合箇所での接触抵抗により発熱して焼けたのか、許容値を超える電流が流れたことで焼けたのか、など
焼損の原因はいろいろと考えられます。
たまにコネクタの接続箇所が黒焦げになっているものを見ますが、これもコネクタピンどうしの接触が不十分なために接触抵抗によって接続箇所が発熱してしまったものです。
今回、バイク屋が不具合の原因をレギュレータと考えた根拠は、
バイク屋としては当然にバイクを売る時点でバッテリーは点検しているわけだから、
あと怪しいのは故障率の高いレギュレータであろうという判断からだと思います。
オルタネータのコイルが断線していたり焼けていないかどうかについても
あらかじめ確認はされていると思います。
しかし、レギュレータについては、劣化状態を確認することができません。
壊れる時期も予測できず、バイクに乗っているときにならないと壊れないものです。
よって、現在のバイクを長く乗りたいのであれば、個人でレギュレータの予備を常備しておくことが望ましいと思います。
注)イラストはSRX600のイメージです。現物どおりではありません。
なお、レギュレータの故障の状態としては、2とおりのものが想定できます。
1つは、部品内部の断線(オープン)、
もう1つは、部品内部の線が別の線とつながってしまうこと(ショート)です。
オープンにより出力に電圧が出ない場合だと、
レギュレータからバッテリーへの充電がされなくなるので、
ランプの点灯などはバッテリーにある電気だけが頼みの綱になります。
しかし、ランプを点灯し続けるとバッテリーの電圧は規定値以下に下がってしまい、それにともないランプは点かなくなってしまいます。
一方、ショートの場合だと、レギュレータ内部の電圧変動により出力電圧が異常に高く
なる可能性があります。
また、電圧を一定にする機能を損なう可能性もあり、その場合にはスロットルをより回すと、バッテリーにかかる電圧もより高くなってしまうことが起こり得ます。
加えて、電圧が高まることでランプの球切れを発生させる恐れもあります。
もしあらゆるランプの球切れが発生したらレギュレータのショート故障の可能性が高いのかもしれません。
また、ショートの場合には、高い電圧によりバッテリーにダメージが加わる恐れがあるので、注意が必要です。
以上、バイクの電気トラブル。レギュレータ故障での一幕についての記事でした。
2017年10月8日